初めまして 時空不動産の水上です。
待望の自社ホームページ:「ランクアップ09」を登場できました。
総合不動産会社を目指し、自らランクアップ・進化して行きます。 又業界全体が、社会の皆様から信頼されるようランクアップ・その一助となるべく働きかけてゆきたいと思います。
皆様からも是非、お気ずきの事、ご要望、ご叱責等々を たまには、お褒めの言葉など、戴ければ更なるランクアップが、出来ると確信しています。
このブログは、一寸いい話 的なエッセイ風にして行きたいと思っています。
次回より「小説アルツハイマーの母」を、連載させていただきます。(週1回ベース)海軍軍人と結婚、終戦を目前にして夫が戦死、3人の子を抱えて奮 闘また奮闘、子の巣立ち後社会福祉に邁進、晩年アルツハイマーとなって終焉を迎えた。???涙あり、笑いあり 昭和を生き抜いた一人の女性の物語 です。
乞う ご期待。
小説「アルツハイマーの母」
序にかえて
平成6年6月21日(火)午後9.30 NHKテレビ国谷裕子アナによるクローズアップ現代「もう外に出ないで」:ある痴呆性老人傷害致死事件 を見た。
既に痴呆性の妻がいる57歳の男性が、急激にボケて徘徊を繰り返す実母に「外に出ないで」と書置きを残して仕事に出る。しかし徘徊は続き、捜しまわる。この繰り返し。 やがて、仕事も止め、妻と母の介護に専念する。その後、精神的にも疲れ果て、母親を傷害致死させる。 その背景を語る30分の番組であった。
見られた方も、多くおられることと思う。
私は、この時間帯、テレビを見ながらビール付の夕食をする、楽しみなひと時であるが、何か「ガーン」と衝撃を受けたようで、食事どころでわなくなった。
番組が終わった後も、アルツハイマー症で徘徊を繰りかえした母のことが、次々と思い出された。 「何をしとるがいネ、はよ書かんがいネ」と母が急かしているように思われた。
母が亡くなってから2年半になる。 小説「アルツハイマーの母」は、構想・章節の体裁・目次みたいなものが作られたに過ぎず、執筆はつい伸び伸びになってしまつていた。
この番組の加害者の男性(実は被害者でもあるが)は、一人で二人の痴呆者を介護した。私の場合は、妻と二人で一人の老人痴呆者の介護をした。比較すれば、四分の一にすぎない。
しかしーーー私が体験したことを母の死後すぐに小説化していて、ひょっとしてこの男性にも知ってもらっていたならーーー少しは違った方向に行き、事件にはならなかったかもしれない。
この男性には間にあわなかつたが、この小説が介護者の心・気持ちに変化を生じさせることができれば、と願い遅まきながら世に問う次第です。
構 成 ( 目 次
第一部 海軍さんの奥さん
{1} G医大柏病院救急部(1)
{2} 同上 (2)
{3} 母の密葬
{4} 母の生い立ち
{5} 父の生い立ち
{6} 父母の結婚
{7} 父母の結婚生活--その1
{8} 同上 その2
{9} 同上 その3
{10} 父の戦死 --その1
{11} 同上 --その2
{12} 同上 --その3
{13} 同上 --その4
{14} 同上 --その5
{15} 同上 --その6
第二部 女傑
{1} 母ちゃん死ぬのは嫌や
{2} 女傑誕生
{3} コブ付きで良いから 嫁に来てくれ
{4} 寺町の伯母
{5} 初めての我が家(持ち家)
{6} 天ぷら屋「天栄堂」
{7} 女傑(1)
{8} 同上(2)
第三部 アルツハイマーの母(認知症)
{1} 語尾に「ありがと」やがてオウム返し
{2} バァちゃん お金持ちやがいネ
{3} ボケたバーちゃん一人置いて 火事でも出された 近所
迷惑や
{4} 妻の提案 深慮遠謀か
{5} 想い出があるがやけど
{6} 我孫子の家へ/長男と同居
{7} 毎週2500円のお小使い
{8} 2kmの散歩道
{9} 毎週 母子の名所旧跡巡り
{10} テーブル一面に ごはん粒
{11} 真夜中の闖入者
{12} 同上 -その2
{13} アラビア語(?)の年賀状
{14} 内科の先生は好き 歯医者の先生は嫌い
{15} バアちゃん専用の特大スカート
{16} 何でも揃う老人介護用品屋さん
{17} 不垢不浄 (指紋が消えた)
{18} 女やさかい
{19} 縫い物・編み物 もうお手上げです
{20} 花壇にうつ伏せ 一晩中か
{21} パトカーで深夜のご帰還(徘徊その1)
{22} ディーケァセンター(託老所)大好き
{23} 金沢帰省(孫の結婚式)
{24} バアちゃんの病医院通い/アルツハイマー病
{25} G医大柏病院 精神内科
{26} 行川(なめりかわ)アイランドの大事件
{27} G医大柏病院 宿直室 (徘徊その2)
{28} バアちゃん 市役所の主事さんみたい
{29} 家の中 泥だらけ
{30} 母子のレジャー行
{31} 一人で着たんか帯まで締めて
{32} 迷子はどっちだ
{33} 金沢帰省−−深夜のお座敷徘徊
{34} 象さんの爪-−衛生
{35} スーパーKのアイドルが店頭ウンチは困ります
{36} 老いへの対応を探る 催し
{37} 寝たきり老人等福祉手当
{38} テレビ見たら ちゃんと寝るがやぞー
{39} サンルームは天国か
{40} 一ヶ月ぶりに<大>が出た(便秘薬)
おわりに
{41} 芝/増上寺 合同慰霊祭
第一部 海軍さんの奥さん
{1} G医大柏病院救急部(1)
1991年12月27日夜9時を少しまわった頃、「ピーポーピーポー」の音と共に救急車が来て、母を連れていった。 妻が同乗していった。
私は、タオル・下着・紙オムツ・オムツカバー・診察券や保険証等取りあえず必要と思われるものを風呂敷に包み、マイカーで追いかけた。
雪が4〜5センチ積もり、ヘッドライトに照らされた雪は小降りだったが非常に寒く、ひょっとすると凍結するかも知れないとおもった。滑り止めチエーンは 入っていたかなー 母の危篤ーーひょっとすると死んじゃうのでわないかーーという時に、チエーンの心配をするとは、 まぁ 私は、落ち着いており、母も 多分大丈夫だろう そう思いーー夜の雪道にスリップしないよう慎重運転で、G医大付属病院救急部へ急いだ。
裏手の救急棟 案内された大きな部屋 白いカーテンで仕切られた一区画 そのベットの上に母はいた。
ゴム管が口に入れられ、ガムテープで貼り付けてあった。多分酸素呼吸しているのだろう。
お医者さんが二人 看護婦さんが二人おられ、一生懸命人工呼吸をしていた,心電図の白い波形が、複雑に波を打ち混乱状態を示していた。電気ショックを与えたり、胸を強く押さえたりの懸命な努力があつた。
母は、苦るしそうな様子は全然なく、されるがままになっていた。手をとる 冷めたい 握りしめる。
「せっかくですが----10時23分です----」 若い医者の声。思わず涙が溢れる。
「ばぁーちやん 迷わず 真っ直ぐ じいちゃんのとこへ行けよなぁ-」 そこまでは声になった。 心のなかで‐-我々3人の子供のために、とことん頑 張ってくれた ばぁちやん 長いあいだ、ごくろうさんでした。本当にありがとう。 三千世界 最高だったと云い続けた夫・親父のところへ行くがやぞー 47年前の30歳の若い奥さんに戻って ほんないと 若い親父(戦死当時・38歳)オフクロさんの顔・姿 若い時しか憶えておらんさけ。--
ある程度覚悟していたとはいえ、人間の死なんて こんなものか あまりにも アッけない。
看護婦さんから「浴衣か何か着替えを持ってきてください」と言われ自宅に帰る。
金沢の弟に電話を入れるが、居ない。妹に電話する 母が亡くなったことを告げる 「 ---ワーッ」 と電話口で泣きだした。
再びG医大病院へ行く。
先程の若いお医者さんから「死因は、急性心不全です。詳しいことを知りたいので、病院解剖させて貰えませんか--勿論強制ではありません」と言われる。
「金沢の弟妹とも相談した上で----」
再度妹に電話を入れる。今度は弟もおり 「解剖が医学の役に立つのなら、それでも良い。兄貴に任せる」とのこと。
「お世話になったG医大での解剖ーー母もきっと了解するとおもいます。よろしくお願いします」と告げた。
明日弟と妹が、車で来るとのことーー私の会社は仕事納めーーお正月も近いので、葬儀はごく内輪だけの密葬とし、会社やご近所にも知らせないことにした。
年が明けて適当な日を選び、金沢で本葬することに決めた。
先程とは ウッて変わって、優しく可愛いい看護婦さんから「身ずくろいができたので、お越し下さい」と言われ母の姿を見に行く。
私が持ってきた白っぽい浴衣を着て、両手が胸のところで組み合わされていた。
顔に薄く白粉がのり、紅く口紅さえつけてあつた。
実に穏やかな、優しい死に顔だった。モナリザのように微笑みさえ浮かべていた。 「ばぁちゃん 美人だぞー」又 心の中で叫んだ。
父の戦死後47年間、阿修羅のごとく鬼子母神のごとく働いて3人の子を育て、喜怒哀楽をその感情のおもむくままに表し、生きた母。晩年、アルツハイマー型老人性痴呆症となった。--今ここに、こんなにも穏やかな安らぎを得てーー眠る。 大往生だ。
その夜は、G医大柏病院の霊安室で、母の遺体だけが眠ることとなつた。
何か気の抜けたようなそのくせホッとしたような複雑な気持ちで、
妻と会話することもなく、マイカーで深夜、我孫子の自宅に戻る。
雪は凍らず、シャーベット状になつていた。
{2} G医大柏病院救急部(その2)
翌日昼過ぎ、指定された時間に、再び救急部を訪れた。
昨日と同じ若い先生が霊安室に導いて下さる。
母は、作日と変わらぬ穏やかな表情だったが頭部は白い包帯でスッポリ覆われていた。午前中に、病理解剖がなされたのだ
私や妻の焼香の後、先生と看護婦さんが、敬虔な態度で焼香された。
そして先生が静かな声で、解剖結果を告げられた。
「亡くなられた水上さんには、自然治癒の結核の跡がありました。胆石の小さなものもあり、糖尿病でもありました。右目の奥に血の塊がありました。脳はーー普通の人は2500gぐらいあるのですが、1080gしかありませんでした」
「1080g! 何歳ぐらいの重さですか?」
「4〜5歳ぐらいでしょうか」
衝撃が走った。アルツハイマー症は、脳が萎縮するとは聞いていたがーー普通の人の半分以下ではないかーー幼児並みの重さに減り 縮んでしまっていたのか!!
あんなバカなことをしてーーこんな幼稚なことをしてーー何でーと思っていたことが、先生から具体的な数値を告げられてーー成程、そうだったのかーー脳が1080gようやく納得できた。
あぁーそれならーーそれをもっと早く知っていたなら、あーもしてあげ こーもしてあげたのに。
何故あの時私は、あんなに真剣になって怒り、怒鳴ったのかーその私の姿を見て、悪びれるどころかエヘラ エヘラ笑っているような母の態度に、かーっときて突き飛ばしたこともあつた。
あぁーなんたる愚かさ 無知--ということのなんたる恐ろしさか
「先生 母は食事時必ず咳き込んでプーッとごはんをテーブル一面に吹き飛ばしていたんですが、喉か食道に何かありませんでしたか」
「何も異常は、ありませんでした。 それから これ解剖のお礼といつてわ何ですが ご霊前にあげて下さい」と金封を差しだされた。
「医学の為に、少しでもお役に立てればと思って了解したことです。お金を貰っては故人に怒られそうです。お返し致しますーー
イエ キマリということでしたらーー一旦頂いて、今度はこのままG医大さんに寄付させていただきます」 そんなにうまくは言えなかったが、それらしきこと を、たどたどしく云って、納めていただいた。(後で 人に聞いたら5000円はいっているとのことーーそんなことより、毎年一回芝の増上寺で、G医大によ る合同慰霊祭の方が本当にありがたかつた。母も喜んでいるに違いない)
死亡診断書2通分の支払いを済ませ、G医大病院手配のT葬儀社の車で、母の遺体を自宅に引き取る。
ついでの事と翌日の密葬のことも、T葬儀社にお願いした。
{3}母の密葬
我が家で最も良い部屋だった一階の座敷ー母が約2年間使って最も酷い部屋になつていた。
この部屋に布団を敷き、西枕で遺体を寝かせる。
仕事納めが終わって帰ってきた娘・息子も手伝って、白い手甲・脚半・白足袋を履かせドライアイスを置き布団を掛ける。その上に魔除けの小刀を載せた。納棺時には、母が大事にしてきた白っぽい和服に着替えさせた。
その日の午後6時過ぎ、深い霧の中、金沢より、個人タクシーをやっている弟の車で、弟・弟の妻・妹そして従兄弟の幸一さんが来てくれた。
その夜はお通夜で、500kmの車旅にもかかわらず、皆、遅くまで母のことを話しあった。
翌29日午前10時、極く身うちの者だけによる密葬を、しめやかにおこなった。11時、出棺 柏の火葬場に行った。
一昨日の雪が嘘のような、良いお天気だった。
火葬の白い煙が、勢いよく噴き流れていた。
妻が、何か悪いことをしたかのように私の弟妹達から離れて、隅の方で畏まっていた。
母の骨は、身体が大きい人だっただけに沢山あった。
お墓が小さいので、喉仏とか小さな骨を拾い骨壷に納めた。
母が亡くなつた直後には、手ばなしで泣いた私だったがそれっきり お通夜でも・密葬でも・火葬後の骨拾いでも涙はでなかった。
思い返せば、ボケて3年とはよくいったものだ。金沢で1年 我孫子で2年 丁度3年だ。
「バァちゃん 計算したように、また最もよい時を選んで死んじゃつたよなぁー」
生前「ボケて人に迷惑をかけたくない ポックリ死にたい」と友達や同輩の人達と一緒に、奈良にあるとかいうポックリ寺参りを何度もしたと聞いた。そのボケ となり、死の恐怖も何もわからなくなって、ポックリ寺すら忘れただろうに、最後は、正にポックリ逝ってしまった。
私には悔いはない。末期には、実母であるのに、女の赤ちゃんの世話をするみたいに、楽しくてならない そんな感じになっていたから。 合掌
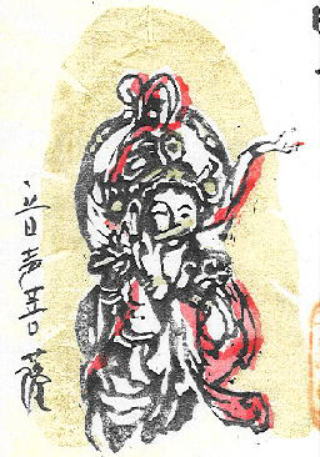
金沢の親族達は、その日の夜中金沢へ向かって帰っていった。
これまで我が一族の中心は、なんと言っても、バァちゃんであった。これからは私が、その代わりをしなければならない。
求心力を高めつつ、やがて遠心力ともなる強い絆を、心がけたいものである。
それにしても私の母は、偉大であった。その生涯を一人の女として、妻として、母親として、その時その時を全力で生き抜いた。
私は子に、孫に、そのまた先の人達に語り伝えて行きたい。
そんな想いで、これから筆を走らせる。(母が私の右手を以って、自分の生涯を語らしめているような即ち自動書記の錯覚を時々感じながら)
[4] 母の生い立ち
母は、大正3年(1914年)5月27日 現在の金沢市玉鉾3丁目K家にて、仁三郎・すず夫婦の子供(3男4女)の末子
として誕生した。
K家は、代々玉鉾村の小作農で貧しい家であつたが、父親の仁三郎や兄達が頑張って、次々と田畑を購入また戦後の農地改革も幸いして増やし 自作農となつていた。
その為か 当時では 珍らしく母は金沢市の私立K女学校に進学している。
身体はおおきく身長・163cm、体重・60kgを超えていた。見るからに健康的で、バレー部に所属 ハーモニカ クラブにも入っていた。学業成績の方は、普通であったようだが、女性らしい流れるようなきれいな字を書いていた。
健康美人ではあったが、いわゆる「美人」と言われたことがない
と語ったことがある。女学校時代の写真を見てもーー成る程なぁーと思われる。
名前が「ミサヲ」だったからか 両親や兄姉達から 「ミサ」 「ミサ」と呼ばれては、可愛がられたらしい。
「5」 父の生い立ち
一方私の父・水上三次は、明治39年(1906年)9月29日、石川県河北郡金浦村字鈴見(現在の金沢市鈴見町)の水上家にて
與三次郎・はつ夫婦の7人の子供(4男3女)の末子として誕生している。
水上家は、代々加賀藩の郷士で名字帯刀・庄屋を勤めた家柄だったようだ。(壇家寺でルーツ捜しをした折、水上という名前が200年以上も前に記載されている)
私の小さい頃父の姉達から「水上家は、村一番 二番と云われた地主であった。小作人は何十人も居り、鶏は千羽以上も飼っていた。與三次郎の7人の姉の中に は、前田藩の家老の家に嫁いだ者も居た。そんな立派な家柄だ。 今は貧乏しているが、よく覚えておいて、決して卑屈にならず やがてお前が大きくなった ら、きっと昔の水上家を取り戻すように・・・・」と何度も聞くかされた。
與三次郎は、久左衛門・もと夫婦の長男であるが、女ばかり7人生まれた後の末子である。ようやく あとつぎが生まれたと久左衛門夫婦は、大喜びで 蝶よ!花よ!と眼の中に入れても痛くない程の可愛がりようで、大事に大事に育てたらしい。
明治の末期、家を新築して成瀬町(今の金沢市鈴見橋付近)に移り住んだ。この家が実に立派なものだったらしいが、火災に遭って燃えてしまった。
同じ場所に同じ家を建てそうだ。この頃から、與三次郎は博打に凝り、又持ち前の人の良さから、他人の保証人となりその殆どで本人が逃げた為、自分が支払わされるハメになった。
悪いことは続くもので、大正の初め 二度目の火災に見舞われ全焼した。家財の殆ども燃えてしまい、仏壇を運び出すことができず、ご本尊と法名の掛け軸だけを持ち出せたらしい。
ご本尊は母の手で表装し直され、現在100代の美川仏壇に収まっているが、未だ窮屈そうだ。おそらく150代かそれ以上の大きな仏壇に収まっていたことと思われる。
この後金沢市板前町(現在の天神町2丁目)移転した。
財力は、完全に無くなっていた。のみならず大きな借金が残った。こんなになっても與三次郎は、働くことを知らず、毎日ブラブラしていたらしい。一家の主人として心労は、人一倍だったと思われるが、如何せん温室育ちの為、経済面の才覚が無かったと思われる。
與三次郎の借金返済の為に、生存していた子供達(長男・次男・二女・三女そして私の父)の苦難がはじまる。
長男の久治・次男の次郎は、大阪の機械工場で働いた。朝早くから夜遅くまで、汗まみれになって働き、借金の返済を続けたそうだ
久治・かしく夫婦に子供が生まれたが、すぐ死んでしまった。かしくは、お乳がでて困った。そんな折 懇意にしていた人の娘と大学生の間に出来た女児があり、貰い受けて養女とし育てた。
その養女・あやえは、中肉中背 色白で、なかなかの美人であった。18歳の頃、儀父母が相次いで亡くなり、金沢の叔母・翠に引き取られた。その後、縁あってF家に嫁いだ。
次郎は、O家の養子となりトモと結婚したが、7年後協議離婚、水上家に復籍した。腎臓を悪くして、47歳の時、亡くなっている。
父親の借金返済に苦るしんだのは、久治・次郎だけではなかった。私の父の2人の姉・翠とトクは、近所の織物工場で働いていたが、水上家が事実上の破産に落ちた時、容姿がすこぶる良かったこともあり、富山県城端町の置き屋の養女とされ、芸妓となった。
翠は、幸いUと言う憲兵将校に見初められ、大正13年に引き出され、結婚した。満州に渡り、かなり上流の生活をしたようだ。子供はなく、終戦前にU氏が、 戦病死したので帰国、金沢の寺町に一軒家を買い求め、得意のお琴・三味線・日本舞踊を教え生計を経てた。前述のあやえを引き取ったのも翠である。その後、 私の弟や妹がすごく面倒を見て貰うことになる。
一方、トクは、昭和4年2月N氏に見初められ結婚した。しかし間もなく夫に先だたれ、寡婦となった。やがて男の子一人連れたM氏と仲良くなり、板前町の家に入り婿の形で同棲した。
だが不幸なことに、又もや死に別れとなり、連れ子の潔を育てた。潔は、赤紙で召集され兵隊となり、満州に渡った。
終戦となり、ソ連に抑留された。(昭和25年日本に復員した。)
一人身になってからトク伯母は、モンペ・地下足袋でしょつ中 山へ行っていた。
山菜・栗。柿。ザクロが収穫だった。
この伯母が行っていた山が、向山の鈴見・若松地域だ。時折、小さい頃の私を連れて行き、「ここは水上の先祖代々の山だった。」と語った。(今は鈴見台の大団地になっている)
私の父・三次は、子供の頃は相当の腕白・キカン坊だったようだ。高等小学校を卒業後、市内電車(現在 軌道は撤去され、存在しない)の車掌をしていた。
17歳の時、徴兵され海軍へはいった。
義務兵役が終わった後も、海軍に留まり職業軍人の道を歩んだ
。
[6] 父母の結婚
父が27歳になった頃、「そろそろ、嫁をもたさねばならない」と2人の伯母を中心に嫁捜しが始まった。
少々キリョウが悪くとも、水上家の跡取りを生める腰の大きな立派な身体の持ち主ーーと言うのが第一条件だったそうだ。
母の兄嫁の実家・K家の紹介で、お見合いとなった。
後に、母から聞いた話だがーー父は、当時機関科の下士官に成り立てで、制服が良く似合っていた。海と相撲で鍛えたガッシリした身体。顔は、いわゆる美男子で特に、眼がとても優しい人というのが第一印象だった。
見合いの席で、ポーッとなり・一目惚れーーこんな人のお嫁さんになれたら、どんなに良いことかーーと思ったそうである。
一方父の方は、美人とはいえないが、健康そうだ。子供を何人も生んでくれそうだ。周りのみなさんが良いというなら、お任せしよう。 ということでトントン拍子に話が進んだ。
昭和9年8月20日 金沢で結婚式を挙げた。父・27歳、母 20歳
の時であった。
婚姻届は、12月3日である。 3ヶ月程遅れているのは、結婚して
うまく行くかどうか 様子を見られた為らしい。
[7] 父母の結婚生活 -その1
母が父のところへ嫁いだ時、父の財産は、机一つ・布団一組・洋服と和服一揃いそして軍服だけ 「何と貧乏な人のところにきたものか」と思ったそうだ。
父の方は、母が御飯を炊くこと・料理することを一切知らないことに、唖然とした そうだ。「深窓のお嬢さんでも料理ぐらいはするだろうに 、農家の末娘が 食事を作れないとは 仕方がない」と結婚翌朝から、お米の研ぎ方・炊き方・おかずの作り方と海軍で習い覚えた食事作りを、母に教え始めたそうである。
住まいは父の職業柄、旧軍港を転々とした。結婚当初は、呉にすんだ。
昭和11年11月 最初の子供がうまれた。 双子で、二人とも男の子だったが、半死半生で生まれ間もなく、相次いでなくなってしまった。父は、大変喜びーーそして大変悲しんだことであろう。
この頃、父は海軍兵曹で、36円月給を貰っていたがその中から必ず10円を、金沢の父親・與三次郎に送金していた。
父の母親・ハツは既に亡くなっている。(昭和7年2月板前町にて死亡)
私の祖母ハツは、写真をみると 髪の長い・撫で肩・実に柔和な顔をした美人である。
水上家が没落した後、娘2人を置き屋に出さなければならなかった母親の気持ちとしてはーーいかばかりであったかーーと察せられる。
小松の尾小屋鉱山に、女ながら、鉱夫となり働らいた。自分の体重と同じ位の重さの鉱石を担いで、頑張ったらしい。
松任の本誓寺(水上家の檀那寺)の前住職から「ハツさんは、この寺によくお参りにおいでた」と聞いたことがある。
小松・松任・金沢と結構距離がある。鉄道馬車があったとわ云え、昔の人はよく歩いたものだ。
昭和13年、母は再度みごもり、9月29日母の実家・金沢の玉鉾で男子が生まれた。陣痛もなく、母が階段を昇ろうとした時、ポロッと生まれ出たらしい。
あわてて産婆さんを呼び、タライにお湯を準備したそうである。
これが 私で 博と名ずけられた。
私が生まれる迄の間、母は「無事に、子供が生まれます様に」と神社に願をかけ、何度もお参りにいった。又「玉の様な美しい子であります様に」と映画俳優の写真をトイレに貼り、毎日一生懸命トイレを掃除し磨いたそうである。
父は、今度は丈夫な子をと願い アレやコレや栄養のある食べ物
を買ってきて母に食べさせたようだ。
特に、牛乳は母の嫌いなものだったらしいが 「お前に飲ますのでわない。お腹の中の子に飲ますのだ」と言われ、鼻を摘んで牛乳を飲んだと聞いた。そのせいか私は、今も牛乳が好きだ。
双子の兄達の後の母の子宮の中だったせいか 私は一人で伸び伸びと大きくなり、生まれた時は、髪もフサフサ、3500gの重さ、五体満足、それこそ玉のような男の子で、元気な産声をあげたらしい。
両親の愛情を一身に受けて、育った
とてもカワイかったらしく、近所の人達から「一寸と貸して 一寸と抱かせて」 と引っ張りダコだったと聞く。
{8} -その2
父の転勤で、舞鶴市行永(現 東町)に住んだ。
父は、軍艦に乗り、南方の島々に行くことが多かった。
それは 外地勤務が内地勤務より給与が高かったためらしい。乗艦手当も付いたようだ。
父が外地に行っている間 母は、半年 一年と父が帰るのを寂しく、待たねばならなかった。
母は、手芸が得意で、特に編み物は先生の資格があり、近所の人達に教えて、生計の足しにもしていたようだ。
私が這いだしたり、歩きはじめると もう寸時もジッとしておらず動きまわるので、長い紐に結び,片端を柱に繋いだそうである。(猿まわしの状態か?)
私が一歳半の頃、母の実家に連れて行かれた折、どうした弾みか、囲炉裏の鍋の煮えたぎるお湯の中に、両手を突っ込んでしまい、夫々5本の指が完全にクッツ イてしまうという大事件があつたそうだ。病院通いのお陰で、何の痕跡も残さず完治した。しかし母や祖母は「大事な跡取り息子が、カタワになるかもしれ ん」、と自分達の不注意を詫び、又大変な心配をしたそうだ。
私が生まれた3年後・昭和16年12月3日弟が舞鶴の官舎で生まれた。 敏夫と名ずけられた。
その5日後、日本海軍のハワイ・パールハーバー奇襲で、第2次
世界大戦が始まった。
父は「イヨイヨ始まったかー!」と感慨ひとしお 奮い立つ思いのようだったと母が漏らした。
{9} -その3
父・三次は酒もタバコものまず、とても柔和で 人一倍、親や家族想いだった。クリスチャンでもあった。物事はキチンとケジメをつけ
また掃除はウルサイ人で、障子の桟を指で撫で ホコリが付いていると「コレは、どうした」と母を叱ったようである。
日本刀を仕込んだ軍刀を、時折打ち粉を振り磨いた。そしてジーッと眺め「軍人の魂だ」と悦に入っていたそうだ。
海軍での出世は、下からのタタキ上げと言うこともあり、遅かった。戦争もたけなわの昭和19年に入り待望の海軍少尉・晴れて将校になった。口髭を生やした中年の海軍士官さんだ。
写真を見ても すこぶるハンサム 制帽・制服。短剣がピタッと似合っている。
私と2歳になった弟を抱き、この素敵な旦那さんを右に幸せで・幸せでたまらないといった感じで座った 母の顔がある。
父が歩いていると、水兵さんが立ち止まり不動の姿勢で敬礼をした。
世間では軍人の世の中 まして海軍は希望と憧れの時代。
2人の男の子を生んだ母は、まさしく 「海軍さんの奥さん」 であった。
戦時下ではあったが、母はいち時の幸せを身いっぱいに感じとっていた。
 |
{10} 父の戦死 -その1
父は、舞鶴の海兵団から帰ると必ず自転車のベルを、チリンチリンと2度鳴らした。これが合図で私と弟は「お父さんダ」と玄関から飛び出すのが常だった
よく海軍病院の方へ散歩に連れていってくれた。
家の中では、アグラをかいた父の膝の右上が私、左上が弟の定位置であった。二人の息子を膝に乗せ、時々膝を揺すり ご満悦の父を覚えている。
物の欠乏していた時代であったが、さすがに海軍だけあって時折、甘いカステラやチョコレートを食べることができた。
昭和19年春 父は、舞鶴海兵団の人事関係の仕事をしていた。
父の友人の一人が、ヒリッピン行きを命じられたが、奥さんが妊娠しており、赴任することに悩んでいたらしい。
義侠心の強い父は、身代わりになり「自分を行かせて下さい」と志願したそうだ。
「行かないでーーアメリカの飛行機や潜水艦で、日本の艦船がドンドン沈められているーー行けば戻って来れなくなるーー自分の番ならいざ知らずーー人の身代わりを申し出るなんてーー私だって、お腹に三人目の子がいる」
「俺が行かねば この戦争は、勝たんのだァ」 と泣きすがる母を平手でなぐりつけた。 そして軍艦に乗りヒリッピンへ行ってしまった。
そして昭和19年10月23日女児がうまれた。
女なら、静子との父の遺言どうりに、名ずけられた。
妹は、戦時中の食料不足の為、生まれた時の体重は、私や弟の時の約半分であったらしい。又私や弟の時は余った程出た母乳が出ず、ミルクや人工乳で育った。そのせいか 弱弱しい身体であった。
{11} -その2
艦の名前は、いまだにわからないが マニラ湾に停泊中、米軍飛行機の爆弾で艦が大破した為、父はマニラに上陸、陸上勤務となった。昭和20年2月 郵便事情が悪い中、やっと届いた父からの手紙がある。
まさしく 遺言状である。
内地帰還の科長に携行依頼したもので 急いで書いた それも鉛筆書きのものだ。よくぞ届いた と思う。今や 我が家の家宝である。
全文 そのまま掲載する。
昨年の今日・1月28日は、楽しく内地に向かって出発した日であるが、1年後の今日は、比島最後の決戦場としてマニラに有り、敵撃滅の機を待つて居ります。
敵ルソン島上陸以来 内地帰還の便もなく 全部当マニラ在帯の同胞人は、各戦闘配置につく事となり(ました)俺も1月中頃より連合工作隊附となり103工作部長承命 服務となりました。
時局は、すでにニユース及びラジオにて聞いて承知して居る事と思います。
比島も今や最大決戦場で お前も武人の妻として いついかなる事が起きるとも 覚悟は充分出来て居る事とおもいます。
大東亜戦争最初の当地 1年前のマニラ 今日の当方面とは、姿こそ同じけれ其の空気に至っては何とも云えぬものがある。
今や健全な者一様に此の地にとどまり、一人一人が盾となり壁となって、敵米の物量の大波を 驕慢の怒涛を 此の比島で押し返さねばならない時が来ました。
去る日の戦闘に於いて幸いに負傷もせず、陸上に移り命令を待って居る内に米軍比島上陸となり、此の決戦に参加する事となりました。
いよいよの場合は一人でも多く殺して 武人として立派に努めをなし散ってゆくから 其の点安心してくれ。
然し最後まで頑張って 何としても当地で押し返さなければならないのである。ただ残念なのは兵器の不足で 特に飛行機の不足は、歯がゆいくらいである。
今迄「一機でも多く」との声を戦地よりとして聞いて居たが、実際戦場に居る者の誰しもがさけぶ言葉だと思ふ。
無事帰へればよし 万一の事を思ひ今後の事を書く。
一、子供も無事生まれた事と思ひますが、生年月日及び名が不明の為に戸籍移動を出来ず 我戦死の報あらば、人事部係員に相談して異動手続をなし、四名分の扶助料を受け取り 残る子供を立派に教育してくれ。
一、賞与及び増俸全部軍事為替にて送金した。然し時局が悪化したので無事つくかは、問題である。運があればゆく。
一、我戦死の報あらば、兄弟とも相談して万事善処すべし。
一、覚悟の事とて、気を強くもって残る子供を立派に教育せよ。
一、結婚十一年余の月日 我儘者の内家・武人の妻として動き
我をして後の心配なく 常仁出征し得たる事を感謝す
我戦死の報あらば、郷里に帰り兄姉と共に仲よく暮らし、子供の養育に努められたし。
霊魂妻子と共にあり 常仁汝らを守らむ。
一、手提げ行李に軍服其の他を入れて、病院船に託せし故 其のつもりで 然し いかなる船も殆ど内地に帰れぬ事と思ふので、あてにせずに居てくれ。
一、女の手一つで 三人の養育は、大変であるが元気を出して、立派に教育してくれ。
妻子の顔を偲び浮かびつつ でわさようなら
1月28日 海軍少尉 水上 三次
なつかしき 妻女え
金沢方面(兄姉) 隣組の皆様へは便り書く間もなき故に、又書いても未着の事と思ふので お前より宜敷く
この便りは、科長が最後に内地へ御帰へりになるので依頼したのです。
俺が無事帰へるか 霊魂が帰へるかの一つ道だ。
いずれにしても武人の妻らしく 取り乱さぬ様
コドモタチニカキオキス
オトウサマハアメリカノヘイタイト、センソウシテイマス。モシカエラヌコトガアッテモ、オマエタチハオカアサンノイフコトヲヨクキイテ、キョウダイチカラヲアハセテ、リッパナヒトニナリオカアサンニ、コウコウヲシナサイ。
オトウサマハ、オマエタチガ、タダシイヒトニナルヨウ、イツモマモッテオリマス。
ヒロシハ、イチバンオホキイノダカラ、オトウトヲカハイガリ、ヨイコニナッテ、オカアサマノオテツダイヲシナサイヨ。
ヤスクニジンジャニハ、オトウサマガイツモオッテ、ミンナヲマモッテオリマス。
1月28日 海軍少尉 水上 三次
{12} -その3
昭和20年3月 戦争も激しくなり、舞鶴から郷里の金沢へ帰ることになった。
母の長兄が国鉄に勤めていた関係でか、当時では夢おぼつかぬ物・貨車一両に一杯の荷物・家財道具を詰めて、金沢に戻った。
板前町で一人暮らししていた、トク伯母の家に同居した。
当時母は、300円位の貯金を持つていたそうだ。300円も出せば、中以上のかなり立派な家が買えたらしい。しかし戦災で次々と都市が焼かれ、何時金沢も 空襲を受けるかもしれない。そんな中、家を買っても仕方がないと郵便貯金にしたままだった。(金沢は戦災をうけず、貯金は、戦後のインフレで紙屑同然と なった。)
同年4月 私は、材木町国民小学校に入学・1年生となった。
広い講堂・体育館の奥まった演台の上に、天皇陛下と皇后陛下の写真があり、カーテンで隠されていた。
朝礼の最敬礼の合図で、全員深深と頭をさげたものだ。
その時カーテンがスルスルと開いたそうだが 「お顔を見ると眼がツブレル」と言われており 見たことはなかった。
暫くして 弟のお腹が、まるで赤ちゃんでも居るみたいに膨れ 痛がって部屋の中を転げまわり 泣き叫んだ。
母が弟を洗濯板に結びつけ 背負って近くの馬坂を上り 大学病院へ連れて行った。
盲腸をこじらせた腹膜炎とのことで、大手術が行われた。
手術は成功だったが、その後も入院して「膿と水分」を吸出していた。お腹に挿し込まれた2本のガラスパイプが、今も眼に残る。
金沢空襲の噂がもっぱらで、私は一人だけ母の実家・玉鉾の家に疎開した。
[13] -その4
昭和20年 夏 夕闇と曇り空を通じて、飛行機の大編隊の爆音が聞こえた。 ブゥゥオーン ブゥーオーン ゴー ゴーーとB-29独特の低い唸りが、幾 波にも重なり金沢の方へ飛んでゆく。「いよいよ来た。B-29の金沢爆撃や」 疎開先の6歳年上・従兄弟の幸一さんが叫んだ。
玉鉾村の人達も飛び出して来、金沢の方を見守った。
でも金沢は、何もなかった。
暫くして 金沢の北東の山並みが、くっきり夕焼けの中に 黒く浮かびあがったように見えた。
「富山が空襲におうとるらしい」と大人の人達がささやきあっていた。その夜じゅう 富山の街は、燃えていたそうだ。音は聞こえなかった。
その時 金沢の板前町にいた母は、大学病院から退院したての
弟を背負い、トク伯母は妹を抱え 一緒に町はずれへ逃げたそうだ。
B-29が来たら金沢がやられる と誰しもがおもっていた。北陸では、一番大きな都市だし 第9師団第7連隊があった軍都でもあったから しかし その後 福井市も空襲を受けたが 金沢は、無事だった。
「終戦が長びけば、金沢がピカドン(原爆)の対象だった」と言う人も居るが---。
{14} -その5
昭和20年8月15日 正午 玉鉾村の国民服を着た班長さんの「大事な放送がある」とのお触れもあり K家のみなさんと一緒に私も戸外の指定場所に集ま りラジオを聞いた。国歌・君ヶ代はわかったが、天皇陛下のお言葉・玉音放送は、雑音が多く 正直言って何を言っておられるのか全然わからなかjつた。
それでも大人達は、「これで終わった 戦争は終わった」と言い合っていた。
私には、終戦ということがよくわからなかったが 何となく 「父も戦地から帰って来るだろう 私も母のところへ戻れる そして親子5人楽しく暮らせるようになるんだ」と思った
空襲こそまぬがれた金沢であるが、食糧難は全国的であった。
国民小学校に戻った私も含め全員で、広い運動場を耕して畑としサツマイモを植えたりした。
進駐軍の命令だとかで、身体中に噴霧器でDDT(殺虫剤)を撒かれた記憶もある。
昭和21年 戦地から次々と復員してくる軍人の中に、父の姿は無かった。
母は、新興宗教の教祖から「ご主人は、ヒリッピンの山中で、猿に助けられ生きている。」と言われ 見ざるー聞かざるー云わざる の3猿の置物を買ってきた。お供えをして、一生懸命父が帰って来る事を祈り待つていた。。
私が小学校2年生となった 春 およそ1年遅れて、一通の手紙が届いた。 戦死公報であった。
<昭和20年6月24日 ヒリッピンのマニラの東部で戦死> というものであった。
遺骨はおろか遺品の類は、一つも無かった。
戦死したからか ポッダムなんとかやらでか 父は、一階級昇進して海軍中尉となっていた。
{15}-その6
史実によれば 第14方面軍司令官・山下大将や他の首脳達の「マニラ無防備都市」にしようとの画策にもかかわらず、海軍部隊(
司令官・岩淵少将)は、市街に立て籠もり米軍に抵抗、昭和20年2月3日から3月2日の1ヶ月間、凄惨な市街戦が行われた。
父も、このマニラ市内で戦ったと思われるが、どの部隊で どの場所で 何時戦死したのかは、今だにわからない。
昭和61年11月15日発行 潮書房「丸」別冊<マニラ海軍防衛部隊の悲劇>峯尾静彦氏の記載により、父が103工作部長をやっていた工作部とは兵器作り (車両のスプリングを利用した日本刀・鉄パイプに爆薬を込めた手榴弾・対戦車用棒付爆雷等の生産)で、運輸部・施設部とトモに古川喜久実少佐参謀の指揮下 にあったらしいことを知る。
後年(s60) 石川県遺族会からの比島慰霊団に参加した母は、マニラの激戦地の一つと云われる所で、石を3ヶ拾って来て父の遺骨代わりとして水上家のお墓に入れた。
先述<マニラ海軍防衛部隊の悲劇>の中に「103が頭につく戦力なき部隊は、できるだけ東方拠点アンチポロ・ボソボソ方面(共にマニラ東方の山中)に送り込んだとある。
この事から推測すれば 103工作部長をしていた父は、マニラ市街戦が始まる前に東方拠点へ移動 南西方面艦隊の編成命令により上部組織・振武集団(横山 陸軍中将)の旗下に入り、山中を転戦 振武集団の組織的戦闘の終了した6月20日頃・戦死公報どうり6月24日マニラ東部で戦死したのかもしれない。
しかし父の最後の手紙では、昭和20年1月28日マニラにあり となっている(マニラ市街戦は2月3日から始まっている)し、小銃が3人に1挺しかない状況下での兵器作りが仕事だったとすれば、最後までマニラにいたと思われる。
さらに陸戦隊の経験のある父は、海軍軍人としてマニラで戦いたかったのではないだろうか 従って事実関係の不明な現在 私は
父がマニラで戦死したと思っている。