第二部 女傑−−母は強し
{1} 母ちゃん 死ぬのは嫌だ
昭和21年6月24日 広報の戦死の日に因んで、板前町の家で父の葬儀が行われた。
父の友人、特に海軍関係の人達から慰めの言葉をかけられ、母は、只 只泣き伏していた。
親戚の人達には「3人の子供を抱えて これからどうしたらよいのか」と問いかけ 励まされても 只泣きじゃくるばかりの母の姿が目に焼きついている。
その日の夜だったと思う。
皆さんが帰られ 静かになった部屋 灯かりも点けず 呆然と座っていた母が、突然弟と妹を側に引き寄せ、私の肩に手をかけ「皆で 死のう」といった。
小さな声だったが、私には ゾクッとする重苦しいものを感じた。
ひよっとすると あれが殺気なのかーーー。
思わず 「母ちやん 死ぬのは嫌だ !!」と叫び、母の胸に飛び込んで泣いた。
わけもわからない筈の4歳の弟と1歳の妹が、その場の異様な雰囲気に怖気ずき ワーワーと泣き出した。
涙の枯れた母が、3人の子を抱えて またまた泣きだした。
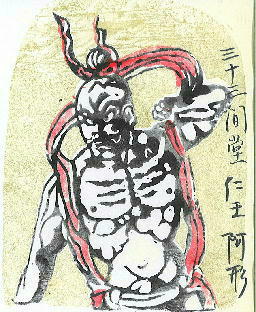
{2} 女傑誕生
この日 母は、人が変わった。
海軍さんの奥さん ではなくなった。
いわゆる「女は弱し されど母は強し」である。
蓄えは、超インフレで紙屑同様になり、毎月送られた父の給与は、「死亡賜金」を最後に無くなった。
食べ盛りの3人の子の食糧確保が、必要であった。
筍生活とはよく言ったものだ。衣類を一枚一枚売っては食糧に換えた。
母は、米の買出しそして女闇屋、化粧品のブローカー、料亭の仲居もした。水上家の親戚・鈴見のT家より 小高い丘の上の畑を借りてサツマイモ作りもおこなった。
このサツマイモ畑の水遣りは、私も手伝ったが 大変だった。母は、水を満杯にした肥桶を天秤棒の両端に吊るし、肩に担いで何度も丘の上まで登り畑に水をやった。
「玉鉾の農家で育った頃は、一切農作業したこと無かったのに 今頃になって 畑仕事だ。アハハハーーー」と苦笑いをしていた。
戦後のインフレで物価は高く 女手による収入は知れており、生活は苦るしかった。
町内の民生委員さんの好意で、金沢市の生活扶助料を受けることになった。それでも 食べることで精一杯だった。
生来明るい性格で 仕事をしながら歌を唄っていた母であるが、仕事・育児・家事に疲れ果て 時々トク伯母にヒス(ヒステリック)を起こして、困らせたりもしていた。
この頃 弟を「養子にやっては、どうか」という話があった。
母は「コンカ(米のヌカ)3升あれば養子にはやらん。水上家の大事な男の子だーー」と断った。そして寺町の翠伯母に預かってもらうことにした
{3} コブ付きで良いから嫁に来てくれ
昭和22年8月 母は、賢坂ヶ辻の小さな菓子店でカキ氷を食べていてK氏と出会った。
K氏は、いろんな商売を手がけ 戦後は闇商人であった。母と出会った頃は、日本酒のブローカー(仲買人)から自前のブランドで
酒商を始めていた。
母より2歳上の35歳、未だ独身であった。
同じブローカーをやっていたせいか意気投合し、K氏に乞われるまま母は、材木町にあったTという屋号の酒店に雇われ勤めることになった。
小立野の有名な造り酒屋Fからお酒を卸してもらい、これに独自のレッテル「K」を貼って売っていたようだ。
このお酒を 取りに行き レッテルを貼り 配達をし 集めた瓶を洗うというのが仕事で、月給は4000円だった。
なにせ 店員は、経営者であるK氏と従業員である母の二人だけ 朝から晩まで自転車に乗り駈けずり回った。
幸い病気もせず健康であった母は、子供の養育に必死になり、更に働き甲斐のある仕事を見付けて、元気一杯頑張った。
一年も経たずしてT酒店は、杜氏を雇い入れ造り酒屋へと発展した。従業員も増えて行った。
経営者で独身のK氏と従業員で未亡人の母との間に、いつしか恋愛感情が芽生え、やがて男と女の関係へ進んでいった。
K氏は板前町の家に来るようになった。
私は小学校の4年生であったが、母を取られるような気がして、又父親以外の人と抱き合う母親にある種の嫌悪感をいだいた。
そしてK氏に対して決して良い顔をしなかった。しかし 母やトク伯母から諭されて、K氏のことを「オジチャン」と呼ぶことになる。
この「オジチャン」が「3人のコブ付き(子連れ)でよいから嫁に来てくれ」と母に結婚を申しこんだ。
母は、実の兄姉や翠・トク伯母達とも相談し又ずいぶん悩んだ。
そして 「やはり3人の子供が大事、水上のままでいる」と、折角のお話を断った。
K氏のT酒店は、更に大きくなった。隣県のK氏の実家からK氏の実母が来て、従業員の取り仕切りを行うようになった。
従業員は皆、陰で「バーバー」(婆婆)とよんだ。
この「バーバ」の肝いりで オジチャンは、若く白くポッチヤリした女の人と結婚した。
オジチャンは、新しく来たお嫁さんに母の事を正直に話してあった。その為か 母に対して嫌がらせみたいな事は、無かったようだ。しかしバーバの母に対する態度は、日毎厳しく 又世間ではオジチャンと母の事を「不倫の仲」と云うようになっていた。
{4} 寺町の伯母
昭和23年3月 弟の敏夫が小学校入学を前に、寺町の翠伯母の
ところから板前町の家に帰って来た。そして 代わりに妹の静子が、寺町へ行くようになった。
翠伯母は、実兄・久次の養女・水上あやえを引き取り養育していた。近くの大きな菓子店に嫁入りさせた後、三味線・お琴・日本舞踊を教えて生計の足しにし、一人暮らしであった。
父戦死後の我が家を見かねて、弟を預かり 今度は妹を預かってくれることになった。
翠伯母は、キレイ好きで 物事にはキチッとしており 躾は厳しかった。又優しい言葉は、殆ど聞いたことが無いひとであった。
しかし水上家の子孫である私達3人に対しては、深い愛情をもっていた。
或る時 弟のオチンチンが風船のように膨らんだ。
「ミミズにオシッコをかけたから」と云うが 多分汚れた手で触りバイ菌が入ったものであろう。医者が「切る」と云うのに対し 翠伯母は「とんでもない 男 の大事なところをチョン切るとは 」と医者から連れ戻し 2日がかりで冷やしたり、和漢の薬をつけたりして遂に直してしまったこともある.
妹の養育費は、1ヵ月3000円であった。この3000円ですら 母の安い月給のなかからの送金であり 生活は、大変であった。
妹が寺町の伯母に預けられ 暫くして 妹は、脊髄カリエスになった。
風邪を引いた後 結核菌が、脊髄についた為だと云う。
妹は、食糧難の時代に生まれ 虚弱体質と云われてきた。
1,2歳の頃はお腹を空かし、左手の親指を哺乳ビンの乳首がわりにいつも吸っていた.
寺町へ行った頃は、かなり肉付いて女の子らしい身体になっていた。父親似のイワユル「美少女」である。
寺町の伯母は、ビックリし大慌てだった。
「あーら エライこっちぁ 脊髄カリエスやて 女の子ながに 背中がセゴになるんやて とんでもない 」とお医者さんへ連れて行き、やがて大学病院へ入院させ、母と代わる代わる 一生懸命看病した。
不幸中の幸いで背骨は、4cm程くの字になって飛び出したが そこで止まった。
母は、当時よく「高いお金を払って寺町の伯母さんに静子を預けたがに こんなことになってしもうて 死んだお父さんに顔むけもできん」とグチっていた。
しかし これは、正しく 気丈だが深い愛情を示した翠伯母のお蔭である。
翠伯母は、終生「私がついておりながら、女の子を片輪にしてしもうて 」と自分を責めていたようだ。
{5} 初めての我が家(持ち家)
昭和25年 トク伯母のところへ同棲したM氏の連れ子・潔さんが、ソ連抑留から復員して板前町の家の2階に入った。
厳しいシベリヤの原野の中で、大変な苦労をされたようだ。
共産党に洗脳されたとか噂があった。その為かどうか 無口で 我々には、とても冷たく感じられた.
母ともうまくゆかなかったようだ。
翌26年 潔さん 結婚。 それを機に 我々水上一家は、味噌蔵町小学校のすぐ近くに 小さな平屋を借りて 引越した。
南道路に面していたが 間取りは悪く、なんだか押しつぶされた感じで暗いイメージの家だった。
こんな家でも 暫くすると 家主が来て どうしたことか 「出て行ってくれ」と云い出した。
その内 家主の依頼を受けたと言う40がらみの男が、毎晩来て母に「出て行け」と迫った。 そうかと思えば 「私の云う事を聞けば、出てゆかんでもよい」と云ったりした。 母を押し倒したりもしたようだ。
母は、これ等の嫌がらせに対し 「もう暫くおらせて下さい お願いします。 3人の子もおるがやしーーー」と必死で哀願した。
一方<こんなことではダメだ どんなチッポケなものでもよい 自分達の家を持たねばならない いや絶対持つてみせる>と決意した。
私も平成4年 不動産業を始めたが この時のことが強く影響しているーーいつの日か きっと沢山の家を持って人様に貸す身になるんだ。
昭和27年2月 トク伯母の住む板前町で10番違いの土地・約40坪の上に、4部屋台所トイレ付き 切り妻屋根2階建て延べ24坪の家を、同じ町内の不動産屋さんに作ってもらうことになった.
竹薮を切り倒し その上に主として廃材の柱を使った 板張りの家であった。屋根は、コンクリートの瓦だった。
都市計画の道路がつくまでは、西側の公道に出る為約15m他人の土地を通行することになる。(都市計画道路は遂につかなかった。)
東側は、隣家に近いと言うことで 又南側は、余地があったが何故か窓がなかった。
記録によると 総額40万円。 資金調達は、母の自己資金10万円 母の兄姉の援助10万円 K氏の補助15万円 借金5万円となっている。
<狭いながらも 楽しい我が家>と言われるように 前述のとうり
家と言えないようなものであったが この家は、母や私達にとり
天国にも登るような素晴らしい住み家であった。
大正年間 2度の大火で持ち家を失って以来、約30年振りに水上家として再び持った それも新築の自宅であった。
母は、<生活保護>を受けている者が家を作るとわ「ケシカラン」と言われないようにと、土地の所有名義は水上家の長男である
私・博にしたものの、建物の方は母の実兄であるK家の與吉名義とした
昭和27年5月20日 引越。 長年の借家住まいにお別れし、念願の自宅に入る。
この3日前 トク伯母危篤との知らせで伯母の家に走り込んだ。
その時 医者が伯母の脈から手を離し「亡くなられました」といった。死因は、心不全だった。
落ち着きのある語り口で優しかったトク伯母は、水上家再興にも等しい持ち家の完成を見て、安心しきったように 眠るが如く静かな顔で逝ってしまった。
私の中学2年生の時である。
{6} 天ぷら屋 「天栄堂」
新しい家ができ移り住んでから 母は、T酒店で更に頑張っていた。借金の返済もあり 朝早くから出勤 帰りも遅いことが多かった。夜の食事の準備は、私の担当となった。
T酒店のKさんと奥さんの間に、子供さんが生まれた。
おとなしかった奥さんも母に対し、何かと嫌がらせをはじめた。
バーバも母に対し、相変わらず厳しく辛くあたった。
考えてみれば 創業当初のパートナーとしては、功績ありであろうが 正妻があれば「めかけ」だ。まして従業員の立場である。
毎日一っ屋根の下で顔を合わすのは、双方にとって嫌で辛いことであったろう。
想いあまった母は、女学校時代の友人・Nさんに相談した。そして T酒店を退職 Nさんのお世話で Sさんが閉店したばかりの
巴町の天ぷら屋・「天栄堂」を引き継ぎ、営業することになった。
昭和28年10月のことである。
2坪位の店は、借り物であり天ぷら油でまみれていた。決してきれいな店とはいえなかった。
収入は少なく、ズーッと赤字が続いた。
オジチャン(K氏)は、その後も月に3〜4回 我々の家に来ていた。そして毎月1万円くらいのお金を、母に下さったようだ。
「博の中学卒業も近いことだし こんな関係はそろそろ終わりにしようか」と母と話し合いが、行われたようだ。
その後徐々に 縁が遠くなっていった。
昭和29年3月 私は、兼六中学校を卒業 弟・敏夫は、味噌蔵町小学校卒業 妹・静子は、同3年を終了した。
私は、家が貧しいのを知っていたので 就職を希望した。
戦死した父の職業からか、海に憧れており 船に乗れる仕事を希望した。海上自衛隊や海上保安庁の公務員は、年が若すぎてダメとのこと。それでは 七尾市の海員養成所へ入ろうと母に申し出た。
「何を云うとるがいね。 いくら貧乏でも高校だけは行かんなん。勉強ができんのなら いざ知らず いい頭して成績もいいがやし遠慮せんと 進学しまっし」
「3度の食事を、2度に減らしても お金のことは、何とかするさかい」
「これからは、 技術を身につけた方が良い」
母は、私の就職希望をハネつけ 逆に進学するよう 私を説得した
そんなことで 私は、金沢市立工業高校 機械科を志望 受験した。 見事合格。 4月には、晴れて高校生となった。
(因みに 1年1組の同級生の中にU孝子・家庭科がおり 現在の私の妻である。 高校時代は、殆ど付き合いが無かったのだがーーー)
高校時代ズーッと石川県の育英資金(貸与)と金沢市母子家庭福祉修学資金をもらった。 家計の一助になっていた。
巴町の天ぷら屋の商売は、当初よりは はやってきたが 儲かる
というところまでは行っていなかった。
私は、学校が終わると店へ行き、店番をさせられた。
母は、私と交替に 自転車に天ぷらを積み 行商に出た。
アルバイトは、小学校高学年の頃から夏休み、冬休みになるとやってきた。呉服屋の店員・薬の配達・菓子屋の店員等である。
従って そんなに苦痛ではなかった。
しかし天ぷら屋の店番は、嫌だった。
私と同じ年頃の女の子が、天ぷらを買いに来ると 何か恥ずかしく-ー来ないでくれー来ないでくれーーと思ったものだ。
昭和31年8月 天ぷら屋の店の持ち主が、店を売りにだした。
母には買える資力はなく、巴町での商売は諦めた。
その代わり 板前町の自宅の台所を改装して、9月中旬営業再開となった。
改装した台所の屋根の上に、真新しい看板「天栄堂」が夕陽を映してまばゆく光った。
{7} 女傑(1)
巴町での天ぷら屋は、商店街にあった。 自宅での天栄堂は、住宅街にあり あまりはやらなかった。
相変わらず母の自転車による営業 行商が主であった。
時折 声をかけられると 橋場町の料亭で 仲居(酌婦)もしていた。
妹は、相変わらず 細身で弱弱しい身体であった。かかりつけのお医者さんに「20歳まで、もたないだろう」と云われ 母は、葬式代にと簡易保険に入ったりした。
弟は、育ち盛りに親が居ず 愛情に飢えていたのか この頃は内向的な性格で、近所との喧嘩・トラブルがよくあった。
物を盗った云々の苦情に対し母は、「うちの子が何したちゅがいね 後家やおもうて メト(バカ)にして 今にみとんまっし----」と大声でわめき 立ち向かっていった。
子供の喧嘩が 大人の喧嘩になったりした。
「生長の家」という宗教に入り、一生懸命「神想感」をしたりした。
しかし持ち前の明るさと世話好きは、続いていた。
遺族会の集まりにもよく顔をだし、又日本民主党味噌蔵校下婦人副部長なる肩書きのもと選挙戦に夢中で走り回ったりした。
高校3年に進級したころから 私は、何としても大学に行きたくなった。 海への憧れもますます強くなった。
受験誌により 大学に行きながら給料を貰えるところがあるのをしった。防衛大学校と海上保安大学校である。
私は、機械科の実習等卒業に必要な単位は、最小限にとどめ 受験科目のみに絞り 猛勉強を始めた。
母は、海に夫を奪われ 次に息子も奪われるのかと反対の意向であった。しかし 父の写真(海軍少尉の正装)に姿勢を正して敬礼しては勉強に励む私の姿を見て、ダンダン諦め やがては合格を祈るになっていった。
防衛大学の入学試験は、12月の初めにあり 国立一期校受験者の腕試しということもあり 当時は32倍という難関であった。
年末に 筆記試験合格通知を貰い、飛び上がって喜んだ。
しかし翌年1月中旬の身体検査で 海自志望では、視力不足と云われ即日 不合格となった。陸上に志望替えする気持ちは、なかった。
天国の後の地獄のような気持ちであった。
引き続き海上保安大学校の受験に、舞鶴へ行ったが 残念ながら一次試験で不合格であった。
やむなく 金沢市内のT機械メーカーの就職試験を受け内定の通知を貰っていた。
防衛大筆記試験合格のことは、学校内でも評判となり 進学担当のO先生が地元の金沢大学の受験を熱心に薦めて下さった。
海がダメなら裁判官にと主旨替えをして法科を受験した。
3月初め 受験の日は、大雪で50cmぐらい積もっていた。
2階の試験場から下を見ると 太陽に向かって両手を合わせている母の姿があった。
4倍程度の倍率であったが、実業高校からは珍しく現役合格であった。
昭和32年4月 桜満開の金沢城石川門をくぐって 私は大学生となった。 金沢大学法文学部は、戦後の新制大学でわあるが 四校の流れをくみ 地元では高い評価を受けていた。そこへ息子を入学させ 母は、本当にうれしくそして誇らしげであった。
{8} 女傑(2)
昭和32年4月 弟・敏夫は、兼六中学校を卒業 京都の友禅染めT社に就職した。
けつして 頭は悪くはなかったが勉強が嫌いで 就職の方を選んだ。
同時に 妹・静子は、兼六中学の1年生となった。
母も 生まれ育った玉鉾のすぐ近くの米丸公民館の主事に、空きができお呼びの声がかかり 喜んで公民館主事となった。
社会福祉事業活動の第一歩でもあった。
片道4KMを自転車で通勤した。
弟は、住み込みで働いて貰った給料の中から1/3を 必ず母に送金してきた。
私の方も 近所の小中学校生の親から家庭教師の依頼が多くあり 又育英資金も貰い 思ったより学資に負担は、かからなかった。
33年8月 弟の勤めていたT社が倒産した為 同じ京都で今度は
食料品販売のO社に転職した。ここに変わってからも母への送金は続いた。
昭和34年夏 O商店から電話があり 弟が日本脳炎という伝染病にかかり、京都市内の病院に隔離されたとのこと あわてて
母と私が隔離病院に直行した。 18歳になっていた弟は、意識はなくただ眠り続けていた。 医師から「硬直しないように 手足の屈伸を続けるように」と指示があり 母と私は、交替で屈伸運動を続けた。
母は、弟の顔を見ながら 時々髪を撫で 何か話しかけながら 夜は 殆ど眠らずに 手足の屈伸運動をしていた。
看病の甲斐あってか 弟は、無事退院 金沢に戻ってきた。
しかし後遺症が脳に残ったのか部屋に引き篭もり 時々家庭内暴力を振るい 家族は暗い生活を強いられた。
しかしこれも2年ほどで元に戻り 弟は、タクシー会社に勤務 運転手として働き出した。
昭和35年4月 妹は、金沢女子短期大学付属高等学校に進学。
昭和36年3月 私は、金沢大学を無事卒業。縁あって総合商社伊藤忠商事に入社。 4月最初の勤務地・名古屋に赴任した。
この間も いろいろな事があったが 主題の「母」のことから少し
離れるので割愛・省略する。縁あれば別稿「僕は、落ちこぼれ商社マン」に譲る。
やがて (昭和39年〜47年)私が結婚、引き続き弟が結婚、そして妹が嫁に行った。
母は、一人暮らしとなった。
この頃 母は、米丸公民館主事から金沢市役所民生課の母子相談員となり、社会福祉事業の仕事に邁進していた。
生活も安定 仕事に生き甲斐を感じ 毎日の通勤が、楽しくてしようがない 特に通勤途上にある金沢城石川門下の四季の移り変わり・風情が 何とも云えないと言っていた。
昭和48年 母は、思い出が一杯詰まった板前町の家を売り、八日市町の家(中古の一軒家、4K)を買い移り住んだ。
板前町の家を買ったのは、前に住んでいたKさんだ。これまで通
行地役権とかで遠慮しながら通っていたのだが 混同とやらで この問題も 解消だ。
昭和50年 3人の子供共同による母の還暦の祝いを、和倉温泉の加賀屋で行った。
還暦とは言え2年遅れており、62歳になっていた。60歳の時 勧奨退職とかで仕事も辞め まったくの一人で生活であった。
時折 高砂大学へ行ったり 草花の手入れをしたり 詩歌を作ったりしていた。
加賀屋では、天皇陛下が泊まられたという超豪華な部屋である。
母は、これまでの苦労を偲び 現在の幸福を噛みしめるようにして大変喜んでいた。